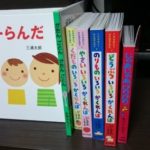2017/03/27

うちの子は、あまり目を合わせようとしません。抱っこしてもそっぽを向き、あらぬ方向を見つめていることが多いです。
たまに笑ったりしますが、コミュニケーションがとれていないような感じがしてしまいます。
まだ二ヶ月だし、視力もそんなに良くないのかも、と思いつつ、調べてみると不安な情報が・・・。
それは「自閉症」。ちょっとその兆候を調べてみたら
・目を合わせない
・体をえびぞりにして泣く
・おもちゃに興味を示さない
などという話が。思い当たるフシがありすぎてこわくなってきました。まさか?!
以下、自閉症について調べたことと、思ったこと。書き出してみようと思います。
sponsored link
自閉症とは
自閉症の診断基準とされるのは、主に以下の3点だそうです。
1. 対人的コミュニケーションが困難。表情、アイコンタクト、身振り手振りなどでコミュニケーションをとり、対人関係を築くのが難しい。自分の興 味があることを、他人と共有できない、等。
2.言葉の発達に、遅れや偏りがある。
3. ある物や行動、考えなどに、強いこだわりを持つ。 ステレオタイプな行動をとる。
また、刺激に対して過敏、全体的に事象を捉えるのが難しい、といった特徴もあるようです。
知能指数がおおよそ70 以上の場合は、「高機 能自閉障害」といわれます。
先天的な発達障害で、親の育て方や接し方のせいで発症するようなものではありません。
言葉の遅れやおかしな行動から、1歳半くらいで様子見となり、確定診断は3歳くらい、というケースが多いようです。
確率的に男の子のほうが多いです。
乳児の診断
前述のように、一歳半くらいでも「様子見」のため、乳児の段階、特に低月齢では小児科でも診断はできないようです。
また、先天性のため、注意していれば発症しないという類のものでもありません。
実際に自閉症の子を持つ親が、乳児の頃を思い返してみると
・ひたすら泣き続けた、あるいは全く泣かず手がかからなかった。
・目を合わせようとせず、抱っこを嫌がり反り返って泣いた。
・あまい笑わず、人への興味を示さなかった。
等の兆候らしきものがあった、という話を見ましたが、それもある子には現れたけれど、ある子には全く現れなかったという個人差があり、判断できるようなものではありません。
ただし、おかしいな?と思ったら、早めに療育に連れて行く、等の対処でその後の発達具合がフォローできるそうです。1歳代と3歳では、脳の発達の程度がだいぶ違ってくるそうなので、まずは療育施設などの発達障害児を支援する施設に行ってみてはどうでしょうか。小児科より詳しい場合もあるそうです。
アイコンタクトの重要性
気になるのは、「目が合わない」ことです。
現在の診断ができないなら、今できることをしたほうが良いのではないでしょうか。
視力の問題もあるかもしれませんが、目を合わせにくい子、というのは存在します。
それならそれで、こちらから積極的に働きかけるべきではなかったかと思い至ったのです。
思い返してみると、ちゃんと目を見てお世話していたでしょうか?自分は慣れない育児で毎日がいっぱいいっぱいになって、不安の中、授乳しながら育児情報をスマホで求めていたりしました。おかげで得た情報はありましたが、その時間、子どもと目を合わせる機会を失っていたのかもしれません。
赤ちゃんにしても、自分を見てくれる人をみつめ返すことを覚えるのではないでしょうか。
何もできない新生児から、ヒトは経験で成長していきます。まずは「対象をじっと見る」ことを教えてあげることから始めようと思いました。これからでも遅くないかもしれません。アイコンタクトの第一歩から、根気よく続けていきたいと思います。
大人の世界でも、アイコンタクトは対人関係の基本です。その基礎を築くのは、赤ちゃんのうちからです。
発達障害のあるなしに係わらず、まずは働きかけを大事にします。
発達障害とオステオパシー
ところで自閉症を含む発達障害に対し、「オステオパシー」という施術があるという情報を聞いたことがありますか?
オステオパシー、聞きなれない言葉だと思いますが、アメリカでは1910年に医学と認定されています。体のゆがみや何らかの制限を解きほぐし、人間の自然治癒力を回復させることによって、体の不具合が良くなる、というものです。
自分も受けたことがありますが、非常にソフトな施術で正直何をされているのかよくわからないくらいでした。でも、身体はちゃんと反応するんです。二年くらいかけて、様々な不調を改善してもらいました。
このオステオパシーで、様々な赤ちゃんの抱えている問題を解消できるとされています。その中に、自閉症などの発達障害に有益な場合があるそうなのです。
(ただし、障害が脳神経や体の構造的異常に起因しない場合もあるので、必ず解消できるとは断言はできません。)
早い時期でのケアが有効です。とても優しい施術のため、生後1ヶ月くらいからでも問題なく受けられます。
日本ではオステオパシーに国家資格はありませんが、日本オステオパシー協会で、国際的な基準を満たす者に「MRO(J)」という資格を与えています。安心して施術を受けられるように、施術者のプロフィールを確認したほうが良いと思います。
以上です。どう思います?
少しおかしなところがあると、皆不安になるのだと思います。
そうならざるをえない状況(ほかに情報がない、母親一人でお世話をしている、等)で子育てしているのですから、仕方ないことかもしれません。
でも、そんな時こそしっかりとわが子を見つめ、向き合っていかないと、と強く思いました。
子どもが起きているときは精一杯相手をし、情報さがしは、寝てからやることににします。






![ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!] ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!]](https://40mam.com/wp-content/uploads/2017/03/C003-150x150.jpg)