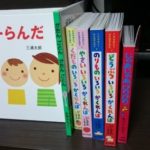2017/03/27

さて、乳幼児期の働きかけがその後に大きく影響する、ということは分かりました。
ではその方法は?何に重点を置けば良いのでしょう?
sponsored link
非認知能力と知育のどちらに重点を置くか
3歳位までは非認知能力を身に着けることを優先すべきと考えます。3歳以降少しづつ知育を取り入れていくことにより、相互に影響を及ぼし合い、高めあうことができます。
あまりに早期の先取り教育は、学年があがるにつれて後々差が少なくなっていきます。
幼稚園受験等を考えないのなら、先取り、詰め込みは幼少時は不要でしょう。
それよりも社会性や自己抑制力を身につけ、「創造性」「自発性」等を伸ばすことこそが、良好な知育の基礎となり、人生の土台作りになるはずです。
早期教育の弊害
早期の教育による弊害もあります。
乳幼児から始められるという「右脳教育」は、「情報を詰め込む」だけのようです。右脳そのものを発達させるという科学的根拠を探したのですが、明確な根拠は見つかりませんでした。フラッシュカードは「考える力」を養わないため、勉強する力が身につかず、9歳以降の学校教育にはついていけない、という説もあります。それよりは自ら思考する力を身に着けさせてあげたいですね。
簡単にできるのは、事あるごとに子供へ「問いかけ」を行うことです。自ら考えることを習慣化させられます。
ところで、右脳を使い計算能力を高める方法としては「そろばん」があります。こちらも賛否両論ありますが、手を使うこと、能動的に行うこと等を鑑みると、脳を総合的に使うというそろばんの方に軍配が上がるように思います。(個人的な意見です)
そろばんと脳については、「日本珠算連盟」のHPに詳しい記事があります。
楽しく行うことで脳の活性が上昇し、情報処理が効率よくなる、などの話もあり、なかなか興味深いです。イヤイヤやっても効果ないのですね。
幼少時の躾と生活習慣
『基本的モラルと社会的成功』という、京都大学の西村和雄教授の論文があります。
子供の頃に以下の4つの躾を受けた者は、成人後の学歴や労働所得が高い、という結果が示されています。
- 「うそをつかない」
- 「勉強をする」
- 「他人に親切にする」
- 「ルールを守る」
モラルの高さが学習習慣を身に着け、また社会性の高い価値判断をする傾向があることが示されました。結局しつけをきちんとする、というのが子供のためにも大切なのですね。
子供は親の言うことよりも、行動を見て育つのですから、我が身を見つめなおす必要もあるかもしれません。一貫した態度が取れるよう、パパ、ママ共に教育方針を話し合っておくべきかも。
共通する働きかけまとめ
様々な情報をまとめてみると、乳幼児期の働きかけは以下が共通するように思いました。
乳児期
スキンシップをする。話しかけをなるべく多く行う。毎日読み聞かせをする。
手指を使うことをさせる。繰り返す。(同じ本を何回も繰り返して読むほうが学習効果が高く効率的)
幼児期
興味を持ったことを徹底してやらせる。問いかけを行い、思考力、判断力、記憶力を養う。生活習慣をきちんと身に着けさせる。ルールを教える。手伝いをさせる。読み聞かせを休まず続ける。(「1日30分の読み聞かせを5ヶ月続けると読書年齢が2年上がる」そうです。)
英語は早い時期にネイティブの発音を聞かせる。
記憶力を高めるには、繰り返すことと、思い出させること。読んだ本の内容、あった出来事、人や物の名前、なんでも言わせる。
最後に
幼児期は、学力の前に身に付けるべき人間性を養う期間です。
自分で考え、選択して、行動する力をつけるには、生活習慣、躾、手伝い、遊び、そして言語の習得が重要です。
あたりまえのことが結論になってしまいましたが、それこそが難しい気もします。
子どもと正面から向き合って、「愛情を持って」「楽しく」を忘れずにやっていきたいですね。






![ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!] ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!]](https://40mam.com/wp-content/uploads/2017/03/C003-150x150.jpg)