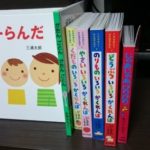2017/03/27

生後100日前後で行う行事「お食い初め」。「百日(ももか)の祝い」とも呼ばれます。
古くは平安時代から、「一生涯、食べることに困らないように」と願いを込めて、食事の真似をさせる儀式です。
早ければ乳歯が生えてくる頃ですね。(乳歯が生えてくる時期は3~9ヶ月頃と、個人差がありますが。)
西洋でも、赤ちゃんの洗礼式にスプーンを使い、「銀のスプーンを贈られた子どもは、一生食べることに苦労しない」という言い伝えがあるそうです。
さてさて、わが子を食うに困らないように、どんな風に儀式を行えばよいのでしょう?
sponsored link
お食い初めの時期
お食い初めを行うのは「生後100日」とされていますが、110日、120日の地域もあります。
乳歯が生えてくる頃の行事なので、皆さんだいたい3~4ヶ月の間に行っているようです。
ちょうど100日でなくとも、赤ちゃんの体調が良い日、出席者の都合で調整すればよいと思います。
儀式の場所
自宅で行う場合が多いと思いますが、実家で行ったり、料亭に行ったりするケースもあります。
お店によっては「お食い初めコース」が設定されているそうです。
料理を作ったり、食器を揃えたりする手間を考えると、気も遣わないで済む外食も捨てがたいですね。
その際は、赤ちゃんを寝かせられる・授乳室がある・オムツ替えができるかどうか、確かめておきましょう。
儀式の参列者
夫婦だけか、その両親(赤ちゃんの祖父母)も参加するか、どちらかのケースが多いようです。
多人数になると誰が食べさせる真似をするか問題になるかもしれませんが、中には「一人一回づつ行った」という体験談があり、なるほど!と思いました。
食べる真似をさせる回数は「3回」なのですが、こだわらなければこれもアリかと。
全員で願ってあげるのも良いじゃないですか?
儀式の流れ
正式には、祖父母などの「養い親」が、食べさせるマネをします。最も年上の人が行うことで、長寿にあやかります。
男の子は男性、女の子は女性が食べさせる真似をします。
食べさせる順番の基本は、『飯→汁→飯→魚→飯→汁』。これを三回繰り返します。
これに歯固めの石が入り、また煮物や香の物がある場合は、
『飯→汁→飯→魚→飯→汁→飯→煮物→飯→汁→飯→香の物→飯→汁→飯→石→飯→汁→飯』となります。
歯固め石は、箸で石にちょんと触れ、その箸を赤ちゃんの歯茎に当てることで、「丈夫な歯が生えるよう」願います。
ごはんを一粒だけ食べさせる「ひとつぶなめ」については、嫌がるようなら真似だけで良いでしょう。
必要な道具・食器
歯固めの石は、神社でいただきます。神社でなければ河原で拾ってもかまいません。終わったら、頂いた場所に返しますが、取っておきたい場合はへその緒と共に保管している人もいるようです。
食器は漆塗りの器で、「男の子は朱色、女の子は黒色(内は朱色)」とされています。赤ちゃんの母方の実家が用意するもの、となっていますが、今は自分たちで用意する事も多いです。
以後も使用できるようにベビー食器を使用する人もいますし、こだわらなくても良いように思います。天然木の食器セットなどは、離乳食にも使えて見た目も落ち着いていて、個人的には心惹かれました。
器の種類は「飯椀、汁椀、平椀、つぼ椀、高杯」の5種類。
・飯椀:赤飯など
・汁椀:お吸い物
・平椀:煮物
・つぼ椀:香の物
・高杯:歯固め石と梅干し
(鯛などの魚と餅は別の皿となります)
お食い初めに合わせて銀のスプーンを贈る人もいるようですよ!
献立
一汁三菜の「祝い膳」が基本です。
・お赤飯・・・または栗ご飯や豆ご飯。白飯でも可。
・尾頭付きの魚(鯛など)・・・縁起物の「めでたい」魚、鯛が一般的。
・吸い物・・・蛤のすまし汁など。
・煮物・・・季節の煮物や筑前煮など。昆布、たけのこ、レンコン等がよく使われる食材。
・香の物・・・漬物や梅干、または紅白なますなど。
あとは、これにお餅を加える場合があります。
セットで取り寄せ
調理された「お食い初めセット」がお取り寄せできます。
祝い箸や、歯固めの石も用意されていて、何の準備も要りません。
京料亭の祝い膳なんて、美味しそう…!
到着日のことを考え、余裕を持って注文しましょう。
自宅で気を遣わずに済ませられるので、気が楽そうです!
以上です。うちはどうしようかな?
儀式というのは形式的になりがちですが、心がこもっていれば、こだわらなくても良いと思います。
どのようにするにしても、想いを込めて行いたいものですね。






![ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!] ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!]](https://40mam.com/wp-content/uploads/2017/03/C003-150x150.jpg)