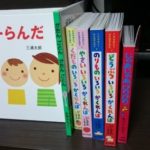2017/03/27
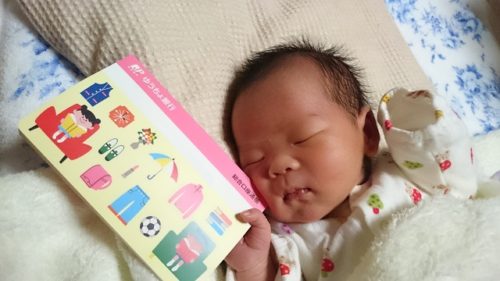
出産費用、幾らかかりましたか?
予想以上に嵩んだりしませんで健康保険から出産一時金が出るとはいえ、新生児管理保育料など、予想もしていなかった費用に驚きました。
少しでも戻って欲しい・・・というのが正直なところ。
確定申告は面倒ですが、医療費控除に挑戦します!
というわけで、出産における医療費控除の詳細について調べました。
sponsored link
医療費控除とは
1年の間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費は、確定申告を行うことによって所得控除を受けることができます。これが医療費控除です。
所得税の控除なので、所得がない人は申請できません。ただし「生計を一にする配偶者・その他の親族」のために支払った医療費はOKなので、同じ世帯で所得がある人が申請することが可能です。
医療費控除の金額は、総所得金額が200万以上の人は
「実際に支払った医療費」-保険金等で補填される金額-10万円
です。最高で200万までとなります。
(注:総所得金額等が200万円未満の場合は、差し引かれる金額は10万ではなく総所得金額等の5%となります)
所得税の対象となる金額が控除で減るわけですから、所得が高い人ほど節税効果が高いわけですね。
「生計を一にする」親族等のために支払った医療費は、その人が所得を有していても「支払った人」の控除の対象になりますから、共働きの場合、どちらも申請することが可能です。所得税の納税率が高い方が申請したほうが、上記のとおり節税効果が期待できます。
出産関係で医療費控除できるもの
・妊婦検診、検査の費用、また通院の費用。
・分娩とそれに伴う入院の費用。
・病院に支払う入院中の食事代。
などは、控除の対象になります。
染色体異常などを診断する諸検査については、一般の人間ドッグや健康診断と同じく「受けた結果、異常が見つかり、治療等を行った場合」は対象になるそうです。羊水検査や胎児ドッグなどですね。
また、「生計を一にする親族等のために支払った医療費」が対象なので、赤ちゃんの医療・入院費も対象となるケースがあります。
健康保険適用の、自己負担分は乳幼児医療費等の自治体による助成でまかなえると思いますが、健康保険適用外の医療費等に対して、対象となるものがあります。1ヶ月検診も控除対象となった人がいました。
ちょっと迷うのは、「新生児管理保育料」。税務署に確認しましょう。
医療費金額計算時の注意点
健康保険などから出産育児一時金や出産費などが支給されますが、その金額は医療費控除の額を計算する際に差し引きます。
生命保険等で、出産のため支払われた保険金があった場合も同様です。(帝王切開などの場合が多いと思います)
健康保険組合から受け取る高額療養費があった場合も差し引きます。
ただし、出産の前後の一定期間、勤務できないために給付される「出産手当金」は、差し引く必要はありません。
実際に戻ってくる金額
医療費控除できる金額として計算された額に、所得税の税率をかけたものが還付金として戻ってきます。
所得税の税率は「課税される所得金額」によって下記のとおりです。
195万円以下・・・5%
195万円を超え330万円以下・・・10%
330万円を超え695万円以下・・・20%
695万円を超え900万円以下・・・23%
900万円を超え1800万円以下・・・33%
1800万円を超え4000万円以下・・・40%
4000万円超・・・45%
なので、仮に医療費が60万かかり、出産育児一時金が42万差し引かれたとすると、
60万(医療費合計)-42万(出産育児一時金)-10万=8万
が医療費控除できる金額となり、その人の所得税率によってその10%(8000円)、20%(16000円)、23%(18400円)・・・のように決まってくるわけです。
また、住民税からの控除もあります。こちらは一律10%です。確定申告すれば、その金額分住民税が安くなります。
一緒に他の医療費も合算できる
例えば歯医者、眼科医などにかかった場合など。病気の治療ために支払った費用も控除対象となり、合算できます。
医療費控除することが確定している年に、歯の治療などを集中して行うと節税になりますね。
人間ドッグ・健康診断の費用については、ふつうは対象外。ただし人間ドッグ等を受けた結果、重大な疾病が見つかり、治療を行った場合は対象になります。
また、医師の診療による不妊症の治療費や人工授精の費用も対象です。
残念ながら予防接種は対象外です。
対象となる交通費
通院にバスや電車など、公共交通機関を利用した場合は、その金額も合算できます。領収書はなくても、その詳細について「日時」「区間」「料金」のメモをとっておくことで申告できます。
タクシーを利用した場合は領収書をもらいましょう。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
出産のため実家に帰省する交通費も、残念ながら対象にはなりません。
ドラッグストアでも領収書は必ず取っておいて!
市販の薬代も、治療や療養に必要なものであれば、一般的な水準の金額なら対象となります。
風邪を引いたときの風邪薬、など購入した場合は、領収書を取っておきましょう。
納税は義務ですが、節税は権利です!
これから子育て費用が、どれくらいのしかかってくるか分からない今、賢く控除を使いましょう!






![ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!] ベビーモニターに「スマカメ」を使ってみました[便利・簡単・安め!]](https://40mam.com/wp-content/uploads/2017/03/C003-150x150.jpg)